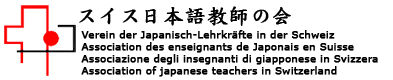青字で下線が付いている講義は、クリックすると講義の資料を閲覧することができます。
無断複写(転用、転載)はご遠慮ください。
※講師の方々の肩書きは研修会開催当時のものです。
| 講師名 | 主な講義内容 | |
| 2023年 | ||
|
笹原 宏之先生 早稲田大学 社会科学総合学術院 教授
|
||
|
会員発表 ゲフダー ギド |
「共に考える日本語を学ぶ楽しみ、教える喜び」 | |
|
東 健太郎 先生 国際交流基金ケルン日本文化センター 日本語教育アドバイザー |
「教科書を教える」?「教科書で教える」?―教師力ブラッシュアップトレーニング | |
| 2022年 | ||
|
石黒 圭 先生 国立国語研究所日本語教育研究領域代表・教授 国立国語研究所研究情報発信センター長 一橋大学大学院言語社会研究科連携教授 |
|
|
|
会員発表 ブランド 那由多 ザッファロン宮本 万基子 |
「実践!小噺!授業に汗と笑いを!」 | |
|
吉岡千里先生 国際交流基金ブダペスト日本文化センター 日本語教育アドバイザー |
||
| 2021年 | ||
|
金田一 秀穂 先生 杏林大学外国語学部 教授 政策研究大学院大学 客員教授 |
「私たちの『日本語』を考える」 | |
|
会員発表 チュウミ晶子 会員発表 カイザー青木睦子 会員発表 宮崎ストレスレ梓 |
||
|
ゲフター・ギド博士 チューリッヒ大学 文学部 東洋学科 |
「『文法』—なぜ、なにを、どうやって教えるか」 |
|
| 2020年 | ||
|
佐藤 慎司 先生 プリンストン大学 東アジア研究部 日本語プログラムディレクター 主任講師 |
「未来を創ることばの教育をめざして」 | |
|
藤光 由子先生 国際交流基金 ロンドン日本文化センター 日本語教育 主任アドバイザー |
||
|
会員発表 ロース・牧野泰子 |
||
| 2019年 | ||
|
野田 尚史(ひさし)先生 国立国語研究所 教授 |
「日本語コミュニケーション教育に必要な言語技術」 | |
|
会員発表 フックス清水美千代 会員発表 スルツベルゲル三木佐和子 ヴェルフレ田邊浩子 会員発表 モジマン中西生子 |
「スイスにおける継承日本語教育の現状」 中等教育について 「欧州、スイスの場合」 「スイスの大学での日本語教育」 |
|
|
渡部 淳 先生 日本大学文理学部 教授 |
「学び方指導の新しい展開 ーアクティブ・ラーニングとアクティビティ」 |
|
| 2018年 | ||
|
村上 吉文先生 国際交流基金トロント日本文化センター 日本語上級専門家 |
|
|
|
近藤 裕美子先生 国際交流基金 パリ日本文化会館 |
||
|
迫田(さこだ)久美子先生 国立国語研究所所 名誉教授・客員教授 |
「第2言語習得理論とその授業への応用」 |
|
|
奥村 三菜子先生 鹿児島キャリアデザイン専門学校 |
||
| 2016年 | ||
|
當作 靖彦先生 カリフォルニア大学サンディエゴ校 教授 |
「21世紀を生き延びるグローバル人材を育てるための日本語教育」 |
|
|
平川 俊助先生 国際交流基金ケルン日本文化会館 日本語教育専門家 |
主な講義内容: 「『学び方』を学ぶために - 自律学習を支える活動を考える -」 |
|
| 2015年 | ||
|
川口 義一先生 早稲田大学名誉教授 |
「外国語教授法の応用による自己表現活動中心の初級日本語教育」 |
|
|
カタリーナ・ドゥツス先生 国際交流基金ケルン日本文化会館 常勤講師 |
主な講義内容:課題遂行型能力を評価する~ロールプレイテストを作る! |
|
| 2014年 | ||
|
嶋田 和子先生 アクラス日本語教育研究所 |
主な講義内容:教材を見る目を養う |
|
|
羽太 園先生 国際交流基金ケルン日本文化会館 日本語教育専門家 |
主な講義内容:「まるごと 日本のことばと文化」徹底解剖 |
|
| 2013年 | ||
|
山内 博之先生 実践女子大学文学部日本文学科 教授 橋本直幸先生 福岡女子大学 専任講師 |
主な講義内容:スイスで学ぶ学習者のための会話教材 |
|
|
福島 青史先生 国際交流基金ロンドン日本文化センター 日本語教育チーフアドバイザー |
主な講義内容:日本語教育における『文化」の大切さについて |
|
| 2012年 | ||
|
由井 紀久子先生 京都外国語大学外国語学部教授 |
「接触場面におけるライティング」 | |
|
熊野 七絵先生 マドリード日本文化センター |
アニメ・マンガの日本語 JFS準拠『まるごと 日本のことばと文化』の紹介 |
|
| 2011年 | ||
|
川口 義一先生 早稲田大学大学院 日本語教育研究科教授 |
「ピンチに強い教授法 — 文法・発音・敬語なんでもOK」 フォーラム 「話す」「読む」「書く」「聞く」をテーマにグループごとに経験を交流する | |
|
磯村 一弘先生 国際交流基金ケルン日本文化会館 |
「音声を教える」「WEB版『エリンが挑戦!にほんごできます』」 | |
| 2010年 | ||
|
小山 悟先生 九州大学留学生センター准教授 |
「教材開発とシラバス・デザイン ―『わかる』授業から『できる』授業への転換―」 | 8 |
| 研修報告 フックス美千代 国際交流基金欧州日本語教師研修会 概要報告 |
「JFスタンダードとCEFR」 | |
| 研修報告 スルツベルゲル佐和子 |
「JFスタンダードを使って:ワークショップ」 | |
|
近藤 裕美子先生 国際交流基金パリ日本文化会館 |
「新しい日本語能力試験 — 改訂のポイントを学習者にどう伝えるか?」 | |
| 2009年 | ||
|
横溝 紳一郎先生 佐賀大学留学生センター教授 |
教師はどうやって学習者のやる気を引き出すのだろう? | 2 |
|
近藤 裕美子先生 国際交流基金パリ日本文化会館 |
書く活動 | 2 |
| 研修報告 フックス美千代 |
国際交流基金欧州日本語教師研修会 概要報告 「JFスタンダードとCEFR」 |
|
| 研修報告 小幡谷 友二 |
「教材作成アイディアの紹介、会話の授業の見直し」 | |
| 研修報告 モジマン 生子 |
国際交流基金海外日本語上級研修会 概要報告 「教科書分析の方法―課分析と練習分析を通して、問題点・課題を見つける」 「第二言語習得理論などを取り入れた、コミュニカティブな教室活動」「参考文献、役に立つインターネット・リソースなどの紹介」 |
|
| 2008年 | ||
|
平田 オリザ先生 大阪大学教授 |
コミュニケーションとしての日本語教育 | |
|
岩澤 和宏先生 国際交流基金ケルン日本文化会館 |
Can−Doを基本にした授業と評価 | |
|
ハインリヒ・ラインフリード先生 チューリッヒ大学東洋学部 |
「教師が知識を与える」から「生徒が自分で知識を得る」へ ―日本語の授業に於ける「教育学上の構成主義」のアプローチと教科書への応用について― | 2 |
| 研修報告 村野千江 |
国際交流基金欧州日本語教師研修会 概要報告 「CEFの理解と実践例」の紹介 | |
| 研修報告 渡辺ロッフェル芽 |
自分の教え方を見直す―会話・聴解・作文の講義を元に | |
| 2007年 | ||
|
北條 淳子先生 早稲田大学名誉教授 |
国際交流基金制作ビデオ教材「エリンが挑戦」の紹介 日本語教育のための文法について学ぶ |
|
|
佐々木 瑞枝先生 武蔵野大学大学院教授 |
生きた日本語を教える工夫 日本語の中のジェンダー表現とイラスト |
|
| 阿部 信泰 大使 在スイス日本国大使 |
日本、スイス間の外交事情 | |
| 研修報告 長嶺孝子 |
欧州日本語教師研修会 概要報告 アイスブレイクとコースデザイン の紹介 |
|
| 研修報告 マテールミ子 |
読むことの指導 の紹介 学習評価 の紹介 |
|
| 研修報告 ケラーゆかり (ミュラー鈴木良子) |
話すことの指導 の紹介 漢字・語彙の指導 の紹介 |
|
| 研修報告 スルツベルゲル三木 佐和子 |
海外日本語教師上級研修とは CEFR/ELPとは 上級研修プロジェクト 日本語能力試験 |
|
| 2006年 | ||
|
加賀美 常美代先生 お茶の水女子大学助教授 |
日本語教師と学習者の一般的な心理問題とその解決について 教育価値観の異文化間比較 |
|
|
沼崎 邦子先生 国際交流基金ケルン日本文化会館 |
新しい日本語能力試験 —どういう点が新しくなるのかー 日本語を継承するーアルゼンチンの日系移住者の実践から学べることー |
|
|
谷道 まや先生 国際交流基金ケルン日本文化会館 |
学習者のアウトプットを引き出す方法 —みんなの日本語、Japanese for Busy People をベースにしてー |
|
| 研修報告 フォーゲルひろみ |
初級クラスのための旅行に役立つ聴解教材(短期用) | |
| 研修報告 クレニン道上まどか |
欧州日本語教師研修会概要報告 授業に活かす様々な取り組みの紹介 |
|
| 研修報告 シュワルツェネッガー竹本真砂子 |
インプット活動の学習設計(読解)の紹介 | |
| 2005年 | ||
|
平高 史也先生 慶應義塾大学総合政策学部教授 |
多言語多文化社会における言語政策 接触場面における非母語話者の言語行動と第2言語教育 |
|
|
戸田 貴子先生 早稲田大学大学院日本語教育研究科助教授 |
欧州の日本語学習者のための日本語教育 | |
| 研修報告 長嶺孝子 |
授業を楽しくする工夫例 初日から使えるIT |
|
| 発表 ロース牧野 泰子 | 文字への興味を引き出す工夫 動詞の活用表の使い方 中だるみ状態脱出の試み |
|
| 2004年 | ||
|
加藤 清方先生 東京学芸大学教授 |
マンガで学ぶ日本語 ジェトロビジネス日本語能力テスト作成法 | |
|
林 明子先生 東京学芸大学助教授 |
読みのストラテジー:テクスト分析と読解指導 会話の対照分析と教育への応用:沈黙は金? | |
|
星 亨先生 ケルン日本文化会館日本語教育アドバイザー |
実践に役立つ教授法 | |
| 研修報告1 Beck阿部真理子 |
漢字知識の基礎の基礎 | |
| 研修報告2 Blaser好美 |
教科書シラバス分析表に対応するロールプレイ | |
| 2003年 | ||
|
鈴木 孝夫先生 慶應義塾大学名誉教授 |
脱西洋中心主義を目指す日本語教育を | |
|
二宮 正之先生 ジュネーブ大学教授 |
日本語ナショナリズムをいかに超えるか | |
|
加藤 清方先生 東京学芸大学教授 |
情報通信技術を利用した日本語教育のあり方 | |
| 2002年 | ||
|
牧野 誠一先生 プリンストン大学東アジア学部教授 |
ウチとソトの言語文化学 「OPI会話能力評価テスト」と実践 |
|
|
川村 よし子先生 東京国際大学商学部教授 |
インターネット時代に対応した新しい読解教育「リーディング・チュウ太」を使った授業の実践とその評価 | |
|
山田ボヒネック 頼子先生 ベルリン自由大学準教授 |
新しい日本語教育をめざして:理論と実践―「ことば化」・言語習得・記号的考察 | |
| 研修報告 Mosimann中西生子 | 擬音語・擬態語を取り入れた授業 | |
| 2001年 | ||
|
太田 亮先生 金沢大学留学生センター助教授 |
日本語教育におけるコンピュータの利用と活用を考える。解説と実践 | |
|
吉岐 久子先生 那須大学都市経済学部助教授 |
カリキュラムと評価。現場における実際的な工夫 解説とワークショップ | 1 |
|
Klopfenstein 朋子先生 チューリッヒ大学日本学部講師 |
漢字のロマン | 1 |
| 研修報告 Schärer-山崎裕美 |
統語論の導入 | 1 |
| 研修報告 Clénin 道上まどか |
コンピュータ、インターネットを使った教材作成 | 1 |
| 2000年 | ||
|
木谷 直之先生 国際交流基金 |
「教科書を作ろう」の説明と応用。自分の現場に会った教案作り 会話力をつける指導方法 | |
|
江副 隆秀先生 新宿日本語学校校長 |
江副式教授法の紹介と実演 「重箱文法」の紹介と解説 |
|
| アニエス ランドルト氏 ジェトロ チューリッヒ事務所 ウルス ロースリ氏 ジャパンコンサルティング社長 ペーター ネルソン氏 |
スイス外務省第二政務局 日本語を外国語としてそれぞれの方法で学んだ3人によるパネルディスカッション | |
| 研修報告 Christen-井上早苗 |
視覚によって学習者の発話を促す教え方 | |
| 1999年 | ||
|
林 さと子先生 津田塾大学助教授 |
学習者の多様性と個別性 直接接触体験を取り入れた会話、聴解の指導 |
|
|
石井 恵理子先生 国語国立研究所 |
多様なメディアを活用した漢字学習 統合的学習活動の設計 |
2 |
|
中島 和子先生 トロント大学東アジア学科准教授 |
異文化環境で育つ子供の日本語教育 年少用OPI コンピュータ活用の作文教育 |
2 |
| 研修報告 Fuchs-清水美千代 |
初・中等教育の教材研究 | |
| 1998年 | ||
|
田中 幸子先生 上智大学外国語学部助教授 |
コミュニカティブタスクの設計と実践 タスクの考え方・ワークショップ |
1 |
|
小屋 逸樹先生 慶応大学助教授 |
一般言語学と日本語の統語的特徴 | 3 |
| 研修報告 Roos-牧野泰子 |
実物教材の授業への生かし方 | |
| 1997年 | ||
|
高見澤 孟先生 昭和女子大文学部教授、 |
ビジネス日本語の現状と展望、日本語の揺れ 実物教材の効果的な利用法 |
2 |
|
ハント 蔭山 裕子先生 昭和女子大文学部講師 |
第二言語取得理論の教授法への応用 | 1 |
| 自動詞・他動詞の指導法、作文と誤用訂正 | 2 | |
|
二宮 正之先生 ジュネーブ大日本学科教授、 |
言語の論理性、文法性、明晰さ 日本語とフランス語の言語、文化比較 |
|
| 研修報告 丸山祥子 |
視聴覚教材の有用性とその使い方 | |
| 1996年 | ||
|
石田 敏子先生 筑波大学文芸、言語学系教授 |
作文、話し方の指導 教案、教材作りのワークショップ | |
|
大曽 美恵子先生 名古屋大学言語文化部教授 |
助詞、副詞節、敬語の問題。モダリティ インターネットの活用 | 1 |
|
小川 誠先生 ケルン日本文化会館 派遣講師 |
直説法を導入したコミュニケーション活動 直説法の基本技術の紹介 |
|
| 研修報告 Kissling-米山香子 |
歌を使った授業方法とその効果 | |
| 1995年 | ||
|
加納 千恵子先生 筑波大・文芸、言語学系助教授 |
漢字の導入法、練習法 最近の教材、教具の説明 |
|
|
小出 慶一先生 群馬県立女子大学助教授 |
視聴覚教材の導入法 最近の評価についての考え方 | |
|
Dr. Heinrich Reinfried先生 スイス国立工科大他 日本語教師 |
スイスにおける日本語教育 スイス人学習者を教える際の問題点 | 1 |
| 研修報告 Sulzberger-三木佐和子 Fredenhagen-村上淳子 |
世界の日本語教育事情 会話能力向上のプロジェクトワークと会話のストラテジー | |
| 1994年 | ||
|
澤井 康子先生 ケルン日本文化会館 派遣講師 |
直説法を使った初級の最初の授業の進め方 教材紹介、文字の導入、ビデオの使い方 | |
|
澤井 康子先生 ケルン日本文化会館 派遣講師 |
初級後半から中級前半のレベルの教え方 条件、受け身、敬語、使役を直説法で | |
右端の数字は講義の録音テープの本数で、「網の目文庫」に入っています。